本文
令和6年度協働管理職研修会を行いました
協働管理職研修会を行いました
本市では、「丸亀市自治基本条例」及び「信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例」、令和6年度から5年間を計画期間とする「第2次丸亀市協働推進計画」に基づき、「市民等の力が活かせる協働のまち・いきいきとした個性豊かで活力あふれるまちづくり」を進めています。その取り組みの一環として、令和6年10月3日(木曜日)に「日々の業務に協働の視点を取り入れるには」と題して、管理職対象の協働研修会を開催しました。
初開催となる今回は、長崎県長崎市市民生活部協働推進室市民力・職員力エンパワーメンターの原田 宏子さん、島根県雲南市政策企画部長(兼)市民環境部脱炭素推進担当統括監の板持 周治さんをお迎えし、行政職員に必要な協働に対する考え方や、長崎市と雲南市それぞれで実施した協働事業の事例をご紹介いただき、協働事業の「種」を考えるグループワークを行いました。

まず、原田さんによる5~6人のグループでのアイスブレイクを行いました。自己紹介と同時に「どんな職場が良い職場だと思うか」について意見を出し合い、グループごとに挙がった「理想の職場像」を全体へ共有しました。グループで出された理想の職場像には「自由に意見を言い合える職場」や「相談し合える職場」、「笑顔がある職場」など、人と人との関わり関することが多くありました。
市役所にあるそれぞれの部署には、それぞれに役割があります。しかし一つの部署だけですべて完結することはできません。所属課や部を超えて連携、共有し合いながら一つのミッションをクリアしていく必要があり、そのためには、部署間の関係も「よい職場」である必要があります。部署間で関係を築き、深めていくためには管理職のリーダーシップが肝心です。また、これは市役所全体が果たす役割も同様です。
原田さんは、「行政職員は、地域において、それぞれの主体との間をつなぐ役割を担っています。職員一人ひとりが人と人とをつなぐ地域のコーディネーターの役割を果たしている、という意識を持つことができれば、とてもよい市役所につながると思いませんか?」と話されました。
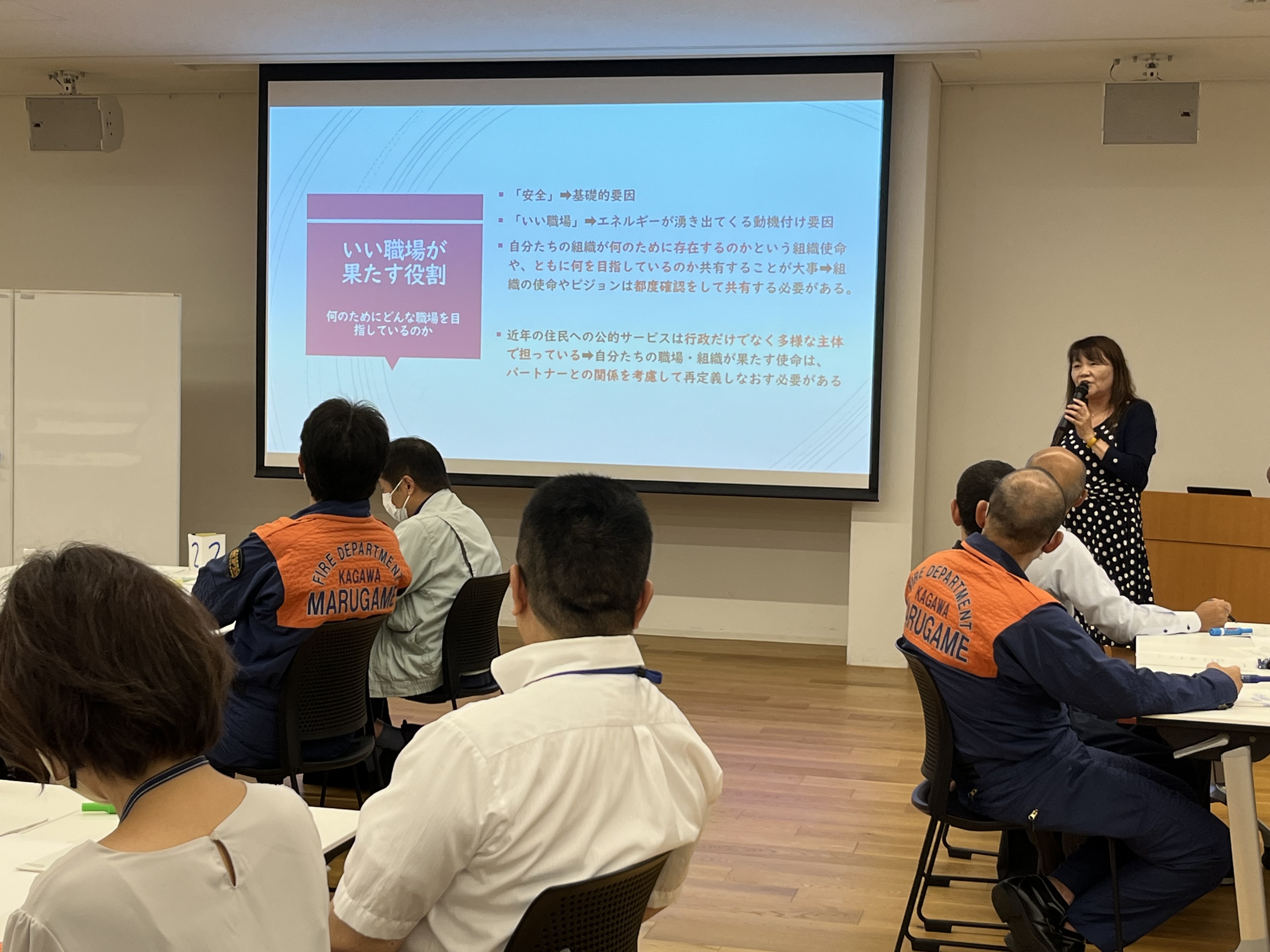
次に、「協働とは」についてです。原田さんは参加者へ「皆さん、協働について考えたことはありますか?協働推進計画を読まれたことはありますか?」と問いかけ、「”協働”は管理職だけではなく、市役所全体に必要な考え方、手法なんです。」と話されました。
地域の課題は様々で多岐にわたります。それを行政だけ、事業所だけ、市民活動団体だけで解決することはできません。異なる組織同士が信頼関係の下、手をつなぎ、それぞれの強みを発揮して協力・強調して課題を解決したり、成果を大きくするための手法のことを「協働」といいます。協働で大切なポイントは”異なる組織”と協力することです。市役所が別の市役所と協働してもできないことは変わりません。同様に大学と別の大学が協働してもできないことは変わりません。しかし、異なる特性を持つ組織同士が協働することで1+1=2以上の相乗効果を生むことができます。それではなぜ協働によるまちづくりが必要なのでしょうか。地域の課題は地域ごとに異なり、その地域の課題はその地域に住む人が一番知っています。なので、市役所と地域全体が協働して地域の困りごとを解決しなければならないのです。
次に実際に雲南市と長崎市で実施された協働事業の事例についてです。まずは板持さんより、雲南市の事例についてご紹介いただきました。
雲南市のまちづくり基本条例では、「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わること」とあり、協働のまちづくりを進めることが明記されています。板持さんは、「協働で大切なことは、対等な関係であることと、補完性だと思っています。協働はよく”役割分担”と表現されますが、やるべきことを分けて壁を作ってしまわないよう、補完し合うという考え方をしています。」と話されました。
雲南市の八日市地区では、行政とコミュニティが協力してリサイクルごみの収集活動を行っています。月に1度だった行政によるリサイクルごみの回収が、コミュニティによる休日の回収日を月に1度設けたことで、月に2度回収することができるようになりました。また、コミュニティによる回収は、回収場所を地域内に3か所設置したことで重い荷物を運ぶ負担を軽減し、行政が回収する際には必要な収集袋が不要となるため、住民の経済的負担を軽減することができているそうです。「コミュニティが主体となって実施することで地域ならではのきめ細やかな対応が可能となっています。」と板持さんは話されました。
また、雲南市のコミュニティセンターでは、地域住民の見守りを兼ねた配食サービスが行われています。配食をする際に、体調や日々の食事、困り事や気になることについて聞き取り、何かあればすぐに行政や病院などの専門機関へ通報ができるというサービスです。地域のコミュニティが行政では担うことの難しい第一発見者の役割を果たしています。

次に原田さんより、長崎市の事例をご紹介いただきました。
長崎市でも自治基本条例「長崎市よかまちづくり基本条例」が制定されており、まちづくりに参画し、様々な担い手と協働しながら”長崎らしい”まちづくりを行うことが明記されています。この自治基本条例は、長崎市民と18か月間をかけた49回のワークショップを行い、作成されたものです。条例の作成から地域全体で行うことで、「自分たちのまちは自分たちでよくしなければ」という共通の意識を持つことができているそうです。
長崎市では、大人のDVを防止する団体「NPO法人DV防止ながさき」と、市の人権男女共同参画室、市教育委員会が協働で、市内の中学3年生を対象にDVの予防教育として若者DV防止啓発事業(出前授業)を実施しました。5月から翌年3月まで、1年間を通して市内22校の中学校を回り、台本を使ってのロールプレイ研修等を実施したほか、生徒だけでなく教員や養護教諭、保健主事を対象とした研修会も開催しました。団体にとっては、行政と協働することで教育委員会や校長会、養護教育部会へデートDV防止への理解を深めることができ、行政にとっては、団体が持つ知識と経験、専門性を活かすことで生徒だけでなくその他関係団体へもDV防止への理解を深めることができた事業となりました。また、団体は授業後の生徒へアンケートを実施し、集計結果を中学校へ提出することで、学校は、生徒の授業を受けての感想や、学校内・生徒間のデートDVに関する現状を知ることができました。
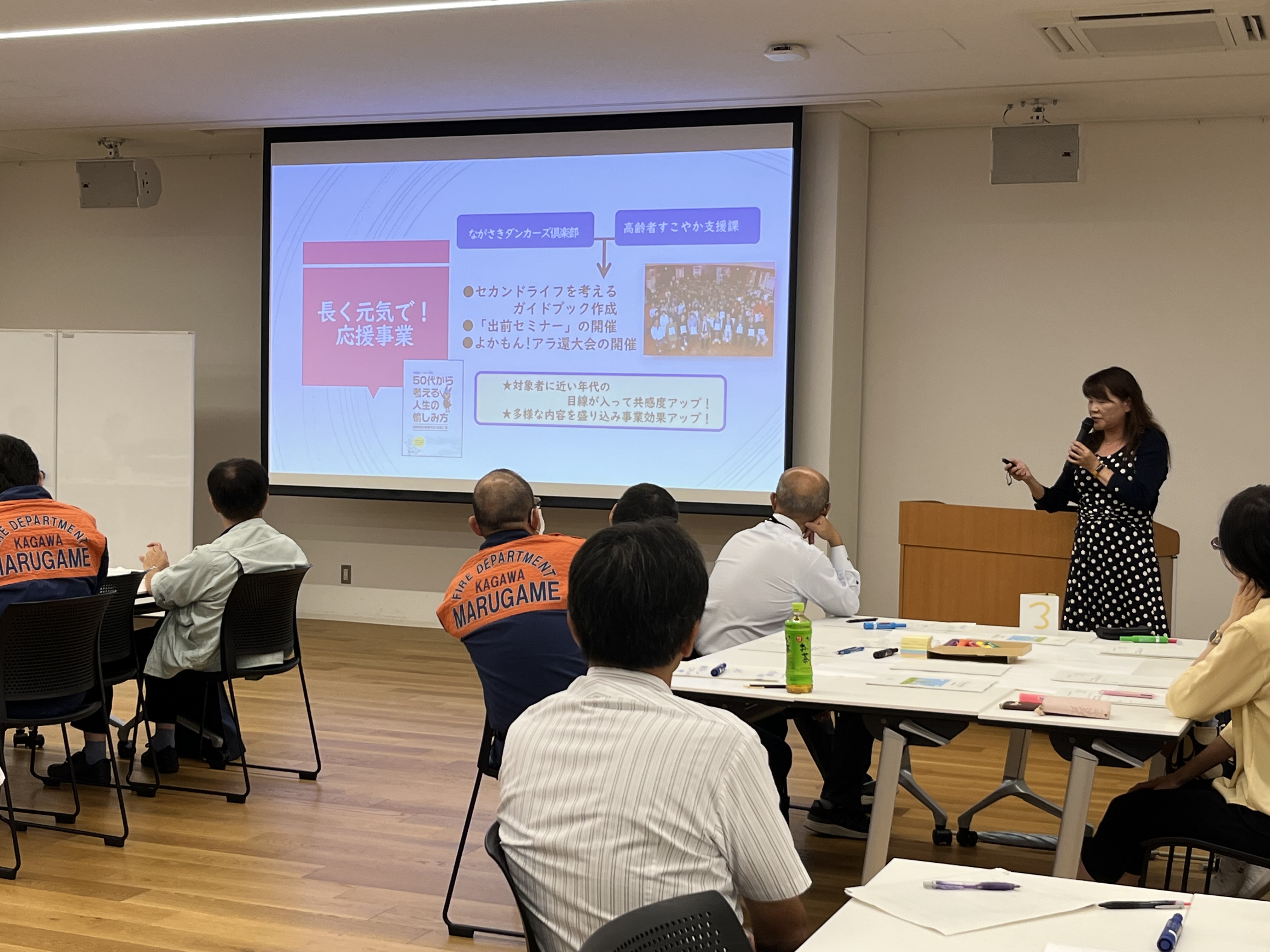
次に雲南市、長崎市の事例を踏まえて、協働事業の「種」を考えるワークショップを行いました。まず、協働の意識を上げるためにはどうすればよいか、どんな事業なら協働することができそうか、の2つについて意見を出し合います。次に、グループで出た意見を模造紙へ書き出し、最後に、これなら協働事業の実施が可能かもしれない、という意見をグループごとに発表しました。
1つ目の協働の意識を上げるためにはという問いには、まずどういった市民活動団体、NPO法人がいて、どんな活動をしているのかを知るための働きかけを行うことや、今回のような協働に関する研修会を開催し、職員の知識と理解を深めていくことが重要だという意見が挙がりました。
2つ目のどんな事業なら協働することができそうかという問いでは、地域と協力し合いながら側溝などの清掃事業、子ども食堂などの居場所づくりに関する事業、高齢者の移動手段の確保などの高齢者支援に関する事業。また、学生と同じ目線に立った情報発信、若い世代との協働といった幅広い分野の事業が挙がりました。


最後に板持さんより、今回の協働管理職研修会のまとめです。
協働の意識を上げるために重要なことは、目線を合わせること、相手の立場に立って物事を考えることです。また、雲南市には協働の8原則があり、板持さんの経験上、「対話」「対等」「目標・取り組む過程の共有」が特に大切だと感じているそうです。板持さんは、「目標を達成するための過程は様々ですが、協働事業を実施する上では、目標をしっかり共有し、過程を同じ立場で一緒に考えるというプロセスが重要となります。職場内でも”自分たちは何を目的としているのか”という目標を常に対話を通して共有し合うことが大切で、そのためには、対等な関係性、雑談をし合える関係性を築くことのできる、風通しのよい職場環境づくりが必要ですね。」と話されました。
研修会に参加した職員からは、「実際にうまくいった事例を紹介いただけたことで、より協働のイメージをつかむことができた」、「常に、何か協働できないか、という視点を持つことができた」、「協働に対するハードルが下がった」などの感想が多くあり、職員の協働に対する意識が少し変わったように感じました。今回の研修で、「協働があたりまえの丸亀市」へ一歩近づくことができたように思います。

