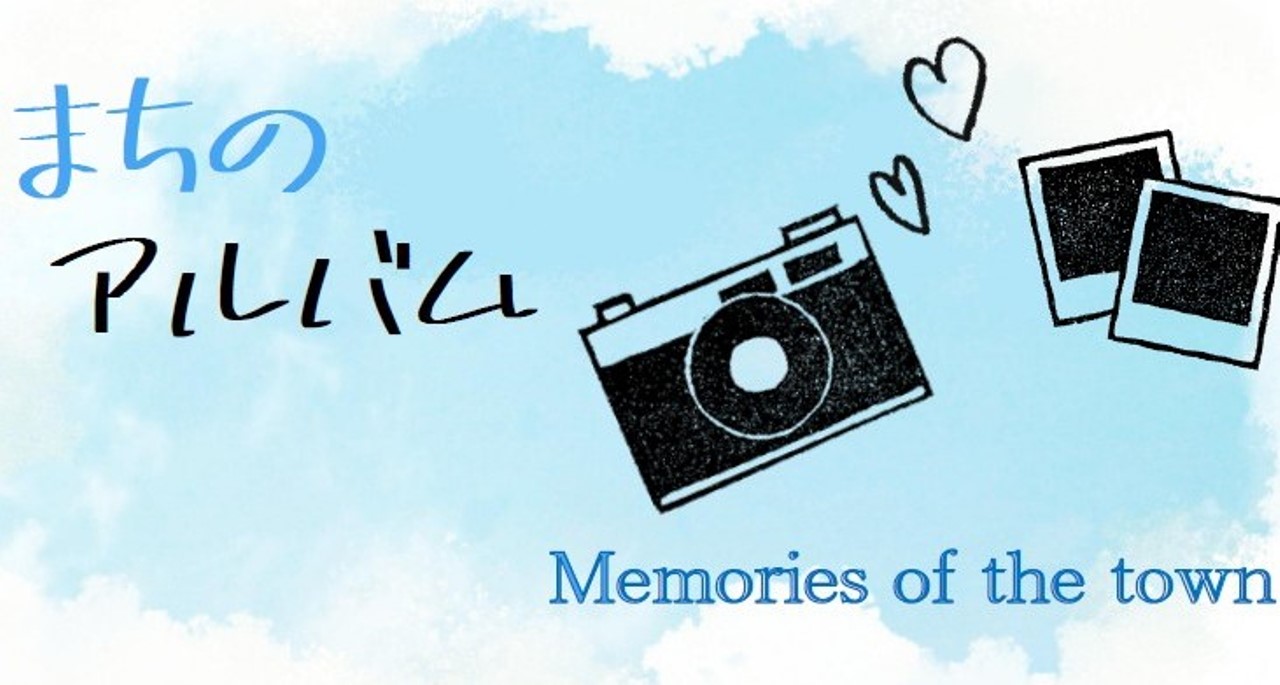本文
時の記念日「時太鼓打ち鳴らし式」
6月10日
丸亀市は、江戸時代に時報として打ち鳴らしていた「時太鼓」を平成18年6月10日(時の記念日)に復活させました。江戸時代と同じ、「大手一の門(別名・太鼓門)」に時太鼓を常設し、現在も正午に打ち鳴らして、時刻を知らせています。
現存天守と大手門があるのは丸亀城・高知城・弘前城の3城ですが、その中でも通年、時太鼓を打ち鳴らしているのは丸亀城だけです。
今年も時の記念日に合わせて「時太鼓打ち鳴らし式」を実施しました。

式では、土居保育所の5歳児14人が、踊り「お祭りドッキュン!」を元気いっぱい披露し、大手門広場をにぎやかにしてくれました。
正午ちょうど、九つ刻(ここのつのどき)になりました。
少し、江戸時代の「時」について…
江戸時代は、夜明け前と夕暮れ時を基準として、1日を「明け方から夕方まで」「夕方から明け方まで」をそれぞれ6等分しました。(半日である12時間を6等分するので、一つが2時間)
また、夜の午前0時と昼の正午を中心に、前後1時間ずつの2時間を「九つ」と決め、時間が経つと「八つ」「七つ」…と数が少なくなり、「四つ」の次はまた「九つ」に戻る仕組みでした。「昼の九つ」は午前11時~午後1時、「昼の八つ」は午後1時~午後3時、「昼の七つ」は午後3時~午後5時…にあたります。
ちなみに、現在の午後3時ころの「おやつ」は「八つ」の時刻が語源と言われています。

では「九つ」の時をおしらせしましょう!
市のマスコットキャラクター「京極くん」ら9人が順番に、「どどん」と太鼓を1回ずつ打ち鳴らしました。
一般参加の人も、時太鼓打ち鳴らし体験ができるので、土居保育所の子どもたちをはじめ、みなさんも時太鼓をたたきました。

お城を見ながら打つ太鼓の音色は、とても爽快な気持ちにさせてくれました。

式では、大木亀丸さんの丸亀城人力車芸人委嘱式も行いました。
「人力車利用1000人目指すぞ!」と亀丸さん。
観光客はもちろん地元の皆さんも、お笑いと観光を楽しめる人力車をよろしくお願いします。